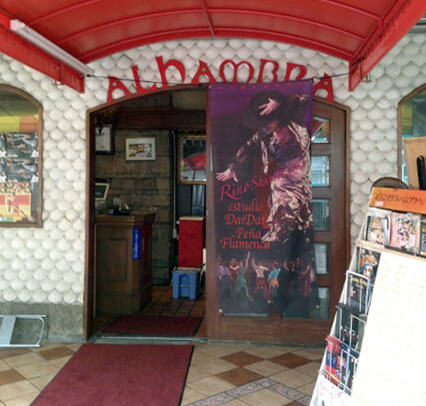横断幕・出力専門店トップ > コラム > 【図解あり】タペストリーの作り方を教えます!
【図解あり】タペストリーの作り方を教えます!
タペストリーを部屋に飾れば、一気におしゃれな雰囲気を演出できます。部屋が殺風景な気がする、もっとインテリアにこだわりたい、自分だけのオリジナリティのある空間にしたいという場合は、タペストリーを取り入れてみましょう。タペストリーは市販のものもたくさんありますが、より自分好みのものを飾りたいのなら、手作りがおすすめです!安価な材料を使った手軽なものからこだわりのおオリジナルタペストリーまで、手作りタペストリーの作り方をご紹介いたします。
目次

タペストリーとは簡単にいうと掛け軸やポスターのようなものです。日本でも海外でも古くから親しまれていたタペストリーですが、近年、おしゃれな手作りタペストリーがSNSなどで話題になっています。
おしゃれなタペストリー飾るだけで、部屋の印象をガラッと変えることができるでしょう。季節や気分、どのときの好みに応じて複数のタペストリーを使い分け、より自分好みの部屋にしましょう。
さらに手作りのタペストリーは、市販のものでは味わえない温かみやオリジナリティを楽しめます。自分好みのタペストリーがなかなか売っていない、市販のアイテムで手軽にタペストリーを作りたいという方は、タペストリーの手作りがおすすめです。
タペストリーの材料は安価で揃えることができます。とくに近年の100円均一ショップには、インテリアアイテムやDIYアイテムが豊富に揃っています。
おしゃれでオリジナリティのあるタペストリーが数百円で手に入るので、市販のおしゃれなタペストリーを購入するよりもお得で、さらに楽しみながら手作りできます。
好きな柄の手ぬぐいがあれば、簡単にタペストリー作りができます。
手ぬぐいはさまざまな柄のものが100円均一でも売られています。和風なデザインから洋風なデザイン、人気の北欧風のデザインなど、種類も豊富です。
手ぬぐいのほかには棒と糸を購入すればOKです。
作り方は、手ぬぐいの上下に棒を巻きつけ、上部の棒に糸をくくりつければ完成です。玄関、お部屋、トイレなど、好きな場所に吊るせば一気におしゃれな空間になります。
桜、海、紅葉、雪など、季節に合った手ぬぐいでタペストリーを作れば、季節感を楽しみながらインテリアを定期的に変えて気分転換することも可能です。手ぬぐいのほかに、薄手のキッチンタオルなどをタペストリーにするという方法もあります。
こだわった柄のタペストリーを作りたいという場合は、手芸用品店でお気に入りの柄を探してみるのもおすすめです。
…タペストリーの注文について
100円均一ショップには海外のカフェのようなおしゃれなデザインの薄手のマットが売られています。これをマットとしてではなくタペストリーにしてしまおう!という方法です。
作り方は、基本的に先ほどの手ぬぐいと同じです。棒に貼り付けて糸を吊るせばOK。マットは手ぬぐいよりも重たいので、強度にだけ注意するようにしましょう。
円形など少し変わった形のマットをタペストリーにする場合は、好きな形に切り取ったり、より大きな布にマットの好きな部分を貼り付けてアレンジしたりという方法もおすすめです。
100円均一ショップで販売されているセメント袋は、インテリアアイテムとして、また収納アイテムとして人気です。適当に服や使わないアイテムを入れておくだけでおしゃれな雰囲気になり、インテリアにこだわる男性からも好評です。
このセメント袋を切り取ってタペストリーにするという方法も人気があります。
文字がプリントされている部分を切り取って、あとは同じように上下に棒を貼り付けて糸でくくり、好きな場所に吊るします。
セメント袋は元来丈夫に作られているので、ちょっとやそっとではほつれたり破けたりしません。
雑に切ってもボロボロになりませんし、かえって大雑把な感じがセメント袋のワイルドな雰囲気とマッチします。

もっとこだわったタペストリーを作りたい!という方に、おすすめのアレンジをご紹介します。
100円均一やホームセンターで販売されている黒板シートを使えば、簡単におしゃれなタペストリーを作成できます。黒板シートは柔らかく、好きな形にカットできます。飾りたい場所に適したサイズに切り取り、上部にはクリップ式のハンガー、下部には重しとなるタッセルを付ければ、タペストリー自体は完成です。
あとは黒板シートに、チョークで好きな文字やイラストを書いていくだけ。
大きな布に棒と糸を取り付けて一枚のタペストリーにして、好きな布をたくさん縫い付けてポケット状にするという方法もあります。
インテリアとしても役立ち、さらに収納アイテムとしても役立てることができます。
不要になったデニムのポケットをそのまま貼り付けてサーフ系のタペストリーにするという方法もあります。
100円均一や雑貨店にはさまざまな造花が販売されています。
この造花と、インテリア用タペストリーを使ったリース風のおしゃれなタペストリー作りもおすすめです。
作り方は、木製風の素材などで格子状になっているタペストリーに、好きな造花を取り付けていくだけでOK。和風の造花を取り付ければお正月などにぴったりですし、春には桜をつけたり、クリスマスにはポインセチアをつけたり、いろいろなアレンジができます。季節に合わせた造花のタペストリーを玄関に飾れば気分も明るくなりそうです。
布にステンシルシートを当てて、好きな色の絵の具を塗るだけでおしゃれな手作り感のあるタペストリーが完成します。
ステンシルシートは市販のものを使ってもよいですが、不要な厚紙やクリアファイルなどを切り取れば自分の好きな文字、絵柄のステンシルシートを作れます。
布の色、素材、文字の大きさ、色、フォントなどで雰囲気が変わりますので、お部屋のインテリアにマッチしたタペストリーのデザインを考えてみましょう。
タペストリーを手作りする方法をご紹介いたしました。お手軽に作れて、お部屋をおしゃれにしてくれるタペストリーは、インテリアにこだわる方には欠かせないアイテムです。
不器用で手作りが苦手、細部でこだわったタペストリーを作りたいという方は、横断幕・のぼり旗・バナー専門店のmakumakuまでご依頼ください。オリジナルタペストリーの作成も承っております。
お気に入りのタペストリーを作って、よりお部屋を魅力的な空間にアレンジしましょう。
タペストリーは、上部のみもしくは上部と下部が棒を入れられる筒仕立てとなっているのが一般的です。上部に棒を通した仕様のものの場合、左右に紐が取り付けられるようになっているので、その紐の中心をフックなどに引っ掛けるのが基本の飾り方になります。
基本の飾り方をする場合、壁にフックを取り付け、紐の中心を引っ掛けてタペストリーが平行になるようにして飾りましょう。フックは画札タイプのものもありますが、貼ってはがせる両面テープで貼り付けるタイプもあります。
ただしフックの耐荷重とタペストリーの重量によっては、フックごと落ちてしまいやすいのが基本の飾り方の難点です。重さがあるタペストリーの場合は、フックを二つ使って二箇所で支えるなど工夫するようにしましょう。
基本の飾り方以外でおしゃれなタペストリーの飾り方を紹介します。
タペストリーを画鋲で刺してポスターのように飾るのも定番の飾り方です。この場合はタペストリーの棒は通しません。棒がないぶんタペストリーの重量も軽く、大きさに合わせて使う画鋲の数を変えればしっかり固定できます。大きなタペストリーを壁一面に貼れば壁紙を変えたように空間の雰囲気も変わります。
フックを使ってタペストリーを飾る場合よりもタペストリーが落ちづらいので、人の動きが激しい場所でタペストリーを飾る場合にもおすすめの飾り方です。
飾り棒とは布を棒に挟んで飾れる棒のことです。マグネットで布を挟めるようになっていて、棒のデザインがさまざまなので、よりスタイリッシュにタペストリーを飾れます。飾り棒は下部も棒で挟むので棒の重さでタペストリーがピンと張り、綺麗に見せることも可能です。
一般的なタペストリーに通す棒を使う時と同様に、フックなどを使って引っ掛ける必要はありますが、インテリアや空間のテイストに合わせた飾り方ができるでしょう。
タペストリーを額に入れ、絵画のようにして飾るのもおすすめの飾り方です。額のデザインを自由に選べるので、インテリアに合わせた飾り方ができます。また額に入れるので、タペストリーが劣化しにくくなったり汚れにくくなったりするのもこの飾り方の特徴です。
額に入れて壁に取り付けることもできますが、そのまま壁に立てかけるだけでもおしゃれに見えるのがこの飾り方のメリットでもあります。棚などの上に置くこともできるので、自由自在に好きなタペストリーを飾れるでしょう。
賃貸物件などの場合は、できるだけ壁を傷つけたくないという方もいるでしょう。
ここからは、壁を傷つけなくない人必見の壁を傷つけないタペストリーの飾り方を紹介します。
突っ張りを取り付けてタペストリーを飾る方法は3つあります。
まず1つ目は部屋の凹凸がある部分に突っ張り棒を取り付け、そこにS字フックをかけて紐をつけたタペストリーを吊るす方法です。この方法で飾れば、壁に直接フックを取り付けた時と同じようにタペストリーを飾れます。突っ張り棒によって耐荷重も違いますが、壁に直接フックを取り付けるよりは、比較的大きくて重さがあるタペストリーでも取り付けやすいです。
2つ目はタペストリー上部の筒部分に直接突っ張り棒を通す飾り方です。この飾り方なら紐がないタペストリーでも簡単に飾れます。また棒に通すことでタペストリーがヨレにくいので、タペストリーのデザインが常にはっきり見えるでしょう。
3つ目は突っ張り棒にダブルクリップをいくつか取り付け、タペストリー上部を挟んで飾る方法です。この方法はタペストリーに紐がない場合でも取り付けられます。また突っ張り棒に直接通した時ほど張りが出ないので、布のたるみが出せるのも特徴です。
最近はポスターや写真などに穴を開けずに壁に貼れる壁用接着剤があります。壁用接着剤は貼ってはがせるので、賃貸の壁にも使用可能です。壁用接着剤を使えば、画鋲を使わなくてもポスターのようにタペストリーを壁に貼れます。
ただし、タペストリーに使用されている布の種類や壁の素材によってはうまくくっつかない場合もあるので、壁用接着剤を購入する前に布の種類や壁の素材をきちんと確認しておきましょう。
インテリアとしてラダーを使用しているという方もいるのではないでしょうか。ラダーの一箇所にタペストリーをかければ、壁に穴を開けなくてもおしゃれにタペストリーが飾れます。
タペストリーのデザイン全体を見せることはできませんが、それが逆におしゃれな雰囲気を醸し出すのでおすすめです。できるだけ全体を見せたいのであれば、タペストリーの裏面に両面テープを貼ってラダーに固定すれば、ずり落ちてしまう心配もありません。
絵画を飾るイーゼルを使ってタペストリーを飾るのも、壁に穴を開けずにタペストリーを飾る方法です。ラダーを使う場合と同様にタペストリー全体のデザインを見せることはできませんが、それが逆におしゃれな雰囲気になります。
ラダーよりも場所を取るため、広い空間で飾りたいときにおすすめの方法です。額にタペストリーを入れた状態で、イーゼルに飾ってもおしゃれでしょう。
タペストリーを飾るうえで気をつけておきたい注意点を紹介します。
タペストリーを飾る場所には直射日光が当たらないようにしましょう。
タペストリーは直射日光が当たるとすぐに色落ちしてしまいます。
また壁に貼るフックで吊るしている場合、直射日光が当たると壁が焼けてタペストリーを貼っていた場所だけ白くなってしまうので、注意が必要です。
タペストリーはそのまま飾っておくと、布に汚れがつきやすいです。こまめにお手入れすればいつまでも綺麗に飾れますが、面倒なのであれば防汚加工をしておくといいでしょう。
布用の防汚スプレーを使えば、汚れがつきにくくなります。タペストリーによっては最初から防汚加工がされているものもあるようです。
タペストリーは布のため、素材によってはすぐに匂いを吸ってしまいます。キッチンにタペストリーを飾ると、タペストリーから嫌な匂いがしやすいのでやめておいた方が無難です。
また同様にタバコを吸う場所に飾ると、タバコの煙をタペストリーが吸って、嫌な匂いを発してしまいます。せっかくタペストリーを飾っても、それが悪臭の原因になっては意味がありません。
タペストリーは布で火が燃え移りやすいので、火を使う場所の近くには飾らないようにしましょう。キッチンのガスコンロ周りに飾るのはNGですし、フックにかけてタペストリーを飾っているものの下でキャンドルやお香を焚くのも危険です。
万が一タペストリーが落ちてしまったら、火事の原因になってしまいます。
部屋の雰囲気を手軽に変えられるタペストリー。市販のタペストリーにもおしゃれなものがありますが、より自分好みにするなら自作のタペストリーを作ってみてはいかがでしょうか。
自作のタペストリーは自分好みの布、吊るすための棒、太い糸や紐があれば簡単に作れます。100円ショップで必要なアイテムを揃えることもできるので、プチプラで作ることも可能です。
タペストリーの顔となる布は自分好みの布を探してほつれないように縫製してもいいですし、手ぬぐいやキッチンクロス、厚手のハンカチなどを使っても構いません。棒を通すための筒を縫うのが大変という方は、布を挟めるタペストリー専用の棒を使えば自作のタペストリー作りは簡単にできます。最近は100円ショップで売られていることもあるので、チェックしてみましょう。
また布にステンシルやアイロンプリントなどで、自作のデザインを施せば、より自分好みのタペストリーになります。Tシャツやデニムを紐状にした「ヤーン」を棒に結んだり、編んだりするだけでも素敵なタペストリーが完成しますよ。
自作でタペストリーを作るときは、布の横の長さに合わせて棒の長さを選べばバランスのいいタペストリーが作れます。棒の長さは、タペストリーの布の横の長さと同じか、3〜10cm程度長いくらいがバランスもいいです。ただ棒の両サイドには紐をつけないと吊るせないので、自作する場合は3〜10cm程度長い棒を選ぶといいでしょう。
タペストリー専用の棒の場合は吊るすための紐がついているものもあるので、それを使えば布の横の長さと棒の長さを同じにすることもできます。どんな仕上がりにしたいかを考えて、棒の長さを選んでみてください。
タペストリーはさまざまな飾り方ができるため、好みや部屋の状態に合わせて適した飾り方を見つけましょう。
ここでは、タペストリーのおすすめの飾り方をいくつか紹介します。

壁にマグネットテープを貼ると、壁を傷つけることなくタペストリーが飾れます。マグネットテープにもさまざまな種類があるので、デザイン性の高いマグネットテープを選ぶと、タペストリーがより映えるはずです。
またタペストリーの周囲にマグネットテープを貼ることで、デコレーションにもなります。
タペストリーを貼り付けるフックがない場合は、後ろ側に両面テープがついているフックを使う方法がおすすめです。
壁に直接貼り付けて使うフックは、耐えられる重さ別にいくつか種類があります。タペストリーは軽いので、それほど強力なものを選ばなくても取り付けられるでしょう。
空間に余裕があってタペストリーを目立つように飾りたい、という場合はイーゼルを使う方法がおすすめです。小さなイーゼルであれば、テーブルや窓付近に飾れます。
大きなイーゼルなら、玄関や廊下、リビングの隅に置けば存在感も抜群です。額縁に入れると、より高級感が出ます。
ラダーとは、はしごのことです。ラダーシェルフ・ラダーラックと呼ばれるはしご型の棚が売られています。ラダーにはタペストリーをそのまま掛けられるため、手間をかけずにおしゃれに飾れるでしょう。
取り外しもしやすく、季節や気分に合わせて簡単にタペストリーが交換できます。

粘着フック・マグネットシートは壁に直接接着面が触れるため、壁紙が剥がれてしまいそうで心配…という方も多いでしょう。そのような時は、養生テープ・マスキングテープを使用します。
養生テープやマスキングテープを壁に貼ってから、その上に粘着フックやマグネットシートを貼り付けましょう。壁紙が保護され、傷つきにくいです。
マスキングテープは文房具屋や100円ショップなどで、さまざまな柄のものが売られています。好みに合うデザインのマスキングテープをいくつか用意しておくと便利です。
テープ・粘着フックだと、すぐに剥がれてきてしまうタペストリーは画びょうやピンを使って飾ります。しかし、画びょう・ピンを使うと壁に穴が空いてしまうため、飾る場所が賃貸物件の部屋ではためらう人が多いです。
針が細いタイプのピンなら、それほど穴が目立ちません。また針そのものに返しがある構造のものであれば、針を抜くときに空けた穴を目立ちにくくしてくれるため、賃貸物件でも使いやすいでしょう。
ただし、針が細いと耐荷重も小さいため、大きなタペストリーを飾るときは注意してください。
柱や壁がある場所にタペストリーを飾りたいときは、突っ張り棒がおすすめです。
なお、突っ張り棒は耐荷重や長さをしっかりチェックしてから購入しましょう。
タペストリーの中でもサイズが小さなものなら、ラミネート加工する方法もあります。ラミネートしたタペストリーを木製ボードなどに飾るだけです。ラミネートしておくと汚れや匂いがつかず、自然とシワも伸ばせます。
余白分に穴を開けられるため、壁だけでなくタペストリー自体も傷つけない点がメリットです。
部屋のインテリアやタペストリーのテイストに合った飾り方をすれば、よりおしゃれな空間を演出できます。
例えばシンプルな部屋にカラフルなモチーフのタペストリーを飾るのであれば、針が細いピンやシンプルな無地のマスキングテープを使用するなどして、なるべくタペストリー自体が目立つようにしたほうがよいでしょう。
また、カントリー調の部屋に合うタペストリーを飾るのであれば、木製のイーゼルやラダーを使い、部屋全体の調和を取るのがおすすめです。
インテリアやタペストリーの雰囲気に合わせて、ぜひ好みの飾り方を追求してみて下さい。
タペストリーは長く、きれいな状態で飾っておきたいものです。
ここでは、タペストリーを飾る際におすすめの場所をいくつか紹介します。
タペストリーを飾る際、直射日光が当たる場所は避けましょう。タペストリーは布製品なので、プリント部分や染めの部分は日光によって変色する可能性があります。特に濃い色は色落ちが目立ちやすいです。
高温多湿の場所に長く置いておくと、カビが発生する恐れがあります。カビは身体にも害を及ぼす恐れがあるので、できないように注意してください。直射日光が当たらない、風通しの良い場所に飾るのがおすすめです。
窓付近・天井に飾る場合は風の流れで匂いが付着することがあります。タペストリーに一度付着した匂いはなかなかとれないため、飾る場所には十分注意しましょう。消臭グッズなどで対策するのもおすすめです。